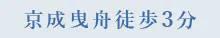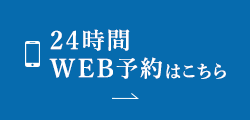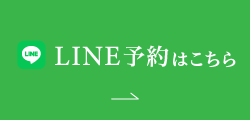男性の泌尿器科
 男性の泌尿器科では、腎臓・尿管・膀胱・尿道などの泌尿器だけでなく、精巣や前立腺などの男性生殖器の病気や症状の診療を行います。また、ED(勃起障害)や男性更年期障害、AGA(男性型脱毛症)といった男性特有のお困りごとについても対応しております。
男性の泌尿器科では、腎臓・尿管・膀胱・尿道などの泌尿器だけでなく、精巣や前立腺などの男性生殖器の病気や症状の診療を行います。また、ED(勃起障害)や男性更年期障害、AGA(男性型脱毛症)といった男性特有のお困りごとについても対応しております。
当院では、患者様のプライバシーを最大限配慮し、経験豊富な泌尿器科専門医が患者様のお話を丁寧に伺い診療しております。お気軽にご相談ください。
よくある症状
排尿に関わる症状

- 頻尿
- 尿漏れ
- 夜間頻尿(夜間に尿意で起きてしまう)
- 尿の勢いが低下している
- 急激な尿意でトイレに間に合わないことがある
- 耐えられないほど激しい尿意で急いでトイレに行く
- 尿を出しづらい、いきまないと排尿できない
- 残尿感がある
- 排尿中や排尿後に痛みを感じる
- 血尿(血が混ざった尿が出る)
- 尿道から膿が出る
- 健康診断で蛋白尿や尿潜血を指摘されたなど
精巣(睾丸)や陰嚢に関わる症状
- 精巣や陰嚢が痛い
- 精巣や陰嚢が大きくなった・小さくなった、左右差がある
- 陰嚢の血管にこぶができているなど
その他
- 健康診断でPSA(前立腺特異抗原)の異常を指摘された
- 性欲が低下した(男性更年期障害)
- ED(勃起障害)など
よくある疾患
前立腺の疾患
前立腺は膀胱の下で精管や尿道を取り囲むように存在する臓器で、精子に栄養を供給する前立腺液を分泌します。
前立腺肥大症
前立腺が大きくなる疾患です。前立腺肥大症が起こると、前立腺の近くにある尿道や膀胱が圧迫され、頻尿などの様々な排尿トラブルが生じます。主な原因は加齢で、中高年以降に排尿トラブルが現れた方は前立腺肥大症が疑われますので、当院までご相談ください。
急性前立腺炎
前立腺で炎症が生じる疾患です。排尿困難・排尿痛・頻尿・発熱などの症状が現れ、進行すると尿閉(尿を出せなくなる)が起こることがあります。急性前立腺炎の可能性があれば、詳しい症状などを確認して尿検査や血液検査を行い、前立腺の圧痛や熱感があるかどうかを確認します。主な原因は細菌感染で、抗生物質を使って治療します。症状が改善しても、治療を途中で止めると抗生物質の耐性菌が残り完治しづらくなるため、医師の指示に従って最後まで治療を続けましょう。なお、重症化すると入院が必要な場合があります。その場合は提携先の医療機関へおつなぎします。
慢性前立腺炎
急性前立腺炎が完治せず慢性化することで起こりますが、その他にも血行不良やストレスなどが原因になると考えられています。排尿に関わる症状は稀で、会陰部や下腹部の違和感・痛みが急に起こりやすいです。このような症状は時間が経つと自然に治りますが、痛む部位が明確でなく、触っても異常が見つからないケースが大半です。
上記のような症状が現れており、消化器の異常が見つからない場合は、慢性前立腺炎の可能性があります。
前立腺がん
日本人男性の中で前立腺がんは発症者数が最も多く、その数は増え続けています。特に50歳以上の方に多く見られ、初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、進行すると排尿困難や頻尿など、前立腺肥大症と類似した症状が現れることがあります。
前立腺がんの早期発見には、PSA(腫瘍マーカー)が有効であり、最近では人間ドックや検診で発見できることも多いです。前立腺がんの発症には遺伝的要因も関係すると言われており、前立腺がん・乳がん・卵巣がんなどの家族歴がある方はご注意ください。当院ではPSA検査を実施しておりますので、50歳以上の方でPSA検査の経験がない方は是非ご相談ください。
精巣・陰嚢の疾患
精巣上体炎
尿道から侵入した細菌が精巣上体に感染し、炎症が生じる疾患です。陰嚢の腫れ・陰嚢内部の痛み・発熱などの症状が起こります。大腸菌などの細菌が原因となる場合もありますが、淋菌やクラミジアといった性感染症の原因菌によって起こることも多いです。精巣上体炎が起こると精子を送り出す働きに異常が生じ、男性不妊が起こるリスクがあるため、気になる症状があればなるべく早めにご相談ください。なお、重症化すると入院を要するため、その場合は提携先の医療機関にお繋ぎします。
精巣がん
発症数は低いですが、比較的若い方に発症がみられるため注意が必要です。早期発見・早期治療によって完治と転移の防止が期待できます。
発症初期は、精巣の腫れ・痛み・硬結・しこり・左右で精巣の大きさが異なるなどの症状が現れ、下腹部の違和感・痛みを伴う場合もありますので、このような症状があればなるべく早めに当院までご相談ください。
なお、患者様の年齢によって、将来の妊娠に備えて精巣精子再手術や精子凍結など精子を作り出す能力を温存するための専門的な治療を要する場合もあります。
尿路・その他の疾患
尿路結石症
腎臓で生成された尿は、尿路(尿管・膀胱・尿道)を通って排出されます。尿路結石症は、尿路に尿中の成分が凝固した結石ができる疾患です。なかでも尿管結石は激しい痛みが起こり、腎盂から送られた結石によって細い尿管が塞がります。尿路結石では、痛みの他にも排尿痛・血尿・頻尿・吐き気・嘔吐などの症状が生じ、急性腎盂腎炎によって発熱症状が現れる場合もあります。レントゲン検査や超音波検査、CT検査などによって結石の大きさやできている場所を調べ、患者様の状態に応じた治療を行います。結石の大きさによっては痛みが生じることなく、長期的に尿管内に留まることで腎機能障害が起こる場合もあるため、早期治療が大切です。
尿路感染症
尿道からウイルスや細菌などの病原体が侵入し、感染が起こることで発症します。尿路の炎症が生じる場所に応じて、精巣上体炎・腎盂腎炎・膀胱炎・前立腺炎・尿道炎など様々な種類があります。精巣上体炎や腎盂腎炎が起こると、陰嚢内の痛み、下腹部や背中の痛み、発熱などの症状が生じます。
女性は尿道が短いため、膀胱炎などの尿路感染症のリスクが高いと言われていますが、男性も前立腺肥大によって発症しやすくなりますので、注意が必要です。
急性尿道炎
淋菌やクラミジアなどの性感染症の原因菌の感染によって発症しやすく、男性では排尿時の違和感・排尿痛・膿が混ざった分泌物が出るなどの症状が現れます。なお、クラミジアに感染しても自覚症状がほとんどなく、気づかないうちにパートナーに感染が広がる恐れがあります。クラミジアは男女いずれも自覚症状が乏しいため、感染が判明したらパートナーも一緒に検査を受け、完治するまで性行為は避けてください。なお、コンドームの使用が性感染症の予防につながるため、性行為の最初から最後まで正しく着用することが大切です。
急性腎盂腎炎
尿道から侵入した病原体が腎臓に達し、感染が起こる疾患です。尿路結石などにより尿路が狭くなると感染リスクが上昇します。排尿痛・背中の痛み・血尿・尿の濁り・発熱などがよくある症状で、高熱が出る場合もあります。腎盂腎炎の治療を受けずに悪化すると、敗血症が起こり命を脅かすリスクもあります。
鼻水やくしゃみ、咳などの上気道の症状は現れずに高熱が出ている場合、急性腎盂腎炎が疑われますので、速やかに専門医による治療を受けることが大切です。糖尿病の患者様・高齢者・別の疾患の治療でステロイドを使っている方などは免疫力が落ちているため、重症化しやすいとされています。怪しい症状があれば、早急に当院までご相談ください。
腎盂尿管がん
腎盂と尿管の内側を覆う尿路上皮細胞にできるがんです。目視で分かるような血尿がよく見られ、血液の塊が排泄される場合もあります。尿路上皮細胞は膀胱まで連続しているため、膀胱がんを併発する場合もあります。喫煙がリスク因子と言われており、60代以上の男性が発症しやすいです。がんが巨大化して尿の流れが停滞すると、水腎症によって腎機能障害が生じる恐れもあります。
腎嚢胞
嚢胞(液体が溜まった袋状の組織)が腎臓に生じる病気です。小さく形状が単純であり、多発していない良性のものは経過観察で問題ありませんが、嚢胞の中で感染や出血が生じる場合があるため、定期的に検査を受ける必要があります。また透析治療を受けている方は、嚢胞性腎がんのリスクがあるため注意が必要です。
腎臓がん・腎細胞がん
腎臓には、尿を生成する腎実質と、生成された尿が集まる腎盂という部分があります。腎臓がんと腎細胞がんは腎実質に生じるがんで、発症には遺伝的要因・高血圧・肥満・喫煙・長期間の透析などが関与すると考えられています。初期段階は自覚症状が乏しいですが、進行すると腹部の腫れや血尿、しこりなどの症状が現れます。近年では治療にロボット手術が選択されることが増えております。当院では、手術前後の患者様に対するフォローアップ体制を整えております。
腎機能障害
腎機能障害は急性腎障害(AKI)と慢性腎臓病(CKD)に分けられます。腎前性腎不全(腎臓への血流が低下する)、腎性腎不全(お薬の影響や炎症)、腎後性腎不全(尿の流れが滞って排出できなくなる)などが原因として考えられます。
急性腎障害では、全身倦怠感・むくみ・尿量減少などの症状が起こるため、すぐに当院までご相談ください。一方で慢性腎障害は自覚症状が少なく、進行に伴って倦怠感・むくみ・息切れ・尿量減少などの症状が起こります。なお、慢性腎不全でこのような症状が起こる場合、既に病状が進行し、治療が難しいことも多いです。ちょっとした異変を感じたら、すぐに当院までご相談ください。
膀胱がん
膀胱がんは環境汚染物質や喫煙が危険因子となると言われており、60代以上の男性に発症しやすいです。発症初期では痛みは現れませんが血尿が出やすく、早期発見できれば負担の少ない内視鏡手術で完治できることもあります。再発を防ぐため、BCGワクチンという上皮がんの治療に効果があるお薬を膀胱内に注入する場合もあります。早期発見が大切な疾患ですので、健康診断の尿検査で尿潜血陽性となった方、もしくは血尿が見られる方はなるべく早めにご相談ください。
神経因性膀胱
膀胱には蓄尿(尿を蓄積する)と排尿(尿を排出する)の働きがありますが、神経因性膀胱によって蓄尿と排尿を適切に調整できなくなります。尿漏れ・尿意消失・頻尿などがよくある症状で、尿が膀胱の中に長期間留まることで腎機能障害や尿路感染症が起こる恐れもあります。
蓄尿と排尿の働きを調整する末梢神経・脊髄・脳などの異常によって膀胱の機能が低下するため、カテーテルや薬物療法などの治療を行います。しかし、完治が難しいケースも多く、根気強く治療に取り組み、長期的な感染予防で腎機能を温存できるようにすることが大切です。
性感染症
性行為を介して感染する病気を総じて性感染症と言います。クラミジアや淋菌、尖圭コンジローマ、梅毒、性器ヘルペス、毛ジラミ症、HIV感染症などが主な病気として挙げられます。オーラルセックスでのどに感染が起こることもあります。性感染症の症状は、残尿感、排尿痛、尿道から膿が出る、血尿、性器のできものなどが挙げられますが、感染しても自覚症状が乏しいことも多いです。また、疾患によっては男女で症状の有無や内容が異なるため、ご自身の感染が判明した場合は、症状の有無に関わらずパートナーにも検査を受けて頂くことが大切です。
男性更年期障害
加齢によって男性ホルモンの分泌が減少し、身体機能に変化が生じることで、男性も更年期障害を発症することがあります。男性更年期障害の症状は、精神症状、身体症状、性機能障害に分類されます。精神症状としては、イライラ・意欲低下・抑うつ・不安などが挙げられます。身体症状としては、ホットフラッシュ(急なほてり・発汗・のぼせ)、息切れ、呼吸困難、動悸、冷え、過眠・不眠、肩こり、耳鳴り、めまい、頭痛、便通異常、関節痛・筋肉痛、全身倦怠感などが挙げられます。性機能障害としては、勃起力や性欲の低下などの症状が起こります。
男性更年期障害は、血液検査で男性ホルモンの数値を調べることで診断が可能で、患者様の病状に合わせた治療で症状の改善が期待できます。気になる症状がありましたら当院までご相談ください。
包茎
包茎は包皮によって亀頭が覆われている状態です。包茎によって包皮炎が頻発している場合や、排尿障害が生じる場合は治療が必要です。軟膏を使った治療で改善できることが多いですが、再発を防ぐために改善した後も継続的にケアすることが大切です。
思春期になると包皮が剥ける方が多いですが、真性包茎(大人になっても包皮が剥けない状態)になると陰茎がんを発症しやすくなりますので、心配な方は一度当院までご相談ください。
なお、嵌頓包茎(包皮を剥いた状態で締め付けが起こり、元の位置に戻せなくなった状態)は緊急処置を要するため、早急に当院までご相談ください。